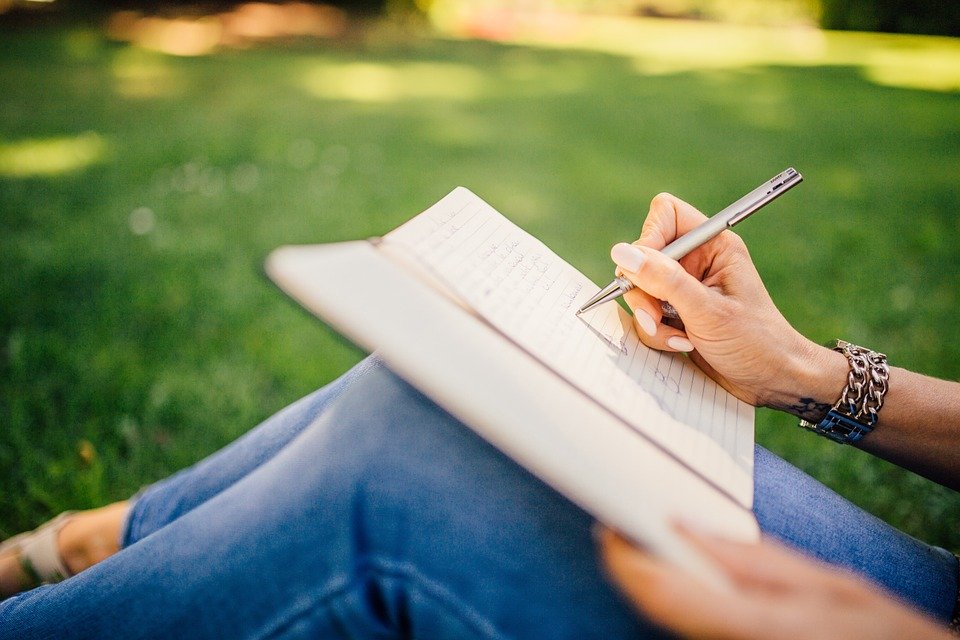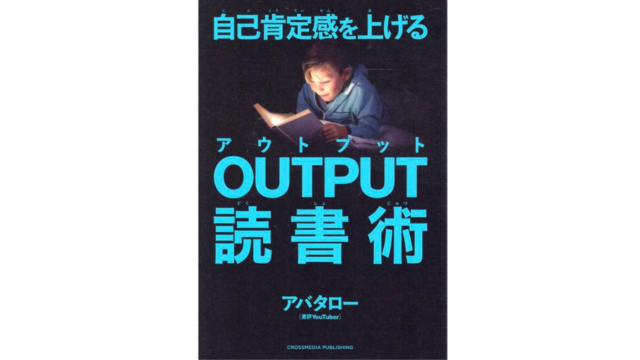行動を継続するための3つのポイント
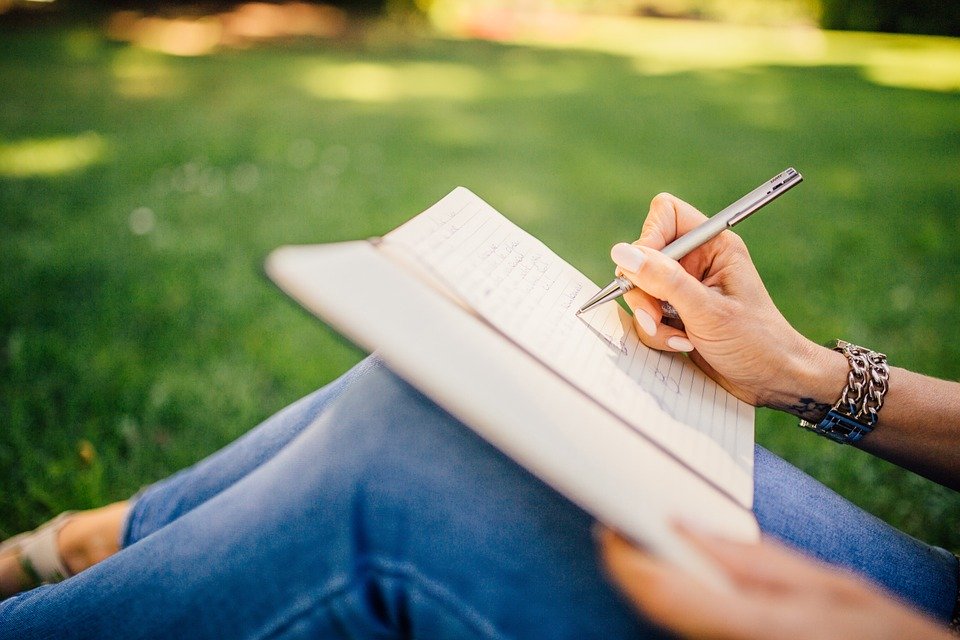
「継続は力なり」という言葉があるように、続けることは能力を伸ばすためには重要な行いです。しかし、勉強や筋トレなど、三日坊主でなかなか続かないという人は多いのではないでしょうか。
「家事で疲れてしまう」「仕事が忙しい」「ついついスマホ見て過ごしてしまう」
など、普段の生活リズムが原因で続かないこともあるかと思います。今日は、継続するためのコツを解説します。
私は毎日noteに記事を投稿する習慣を今年から開始しました。今のところ、120日間、投稿を継続できています。習慣づけするためのポイントは、以下の3つです。
- 他人に話すこと
- 毎日やること
- すべてをやらないこと
ひとつずつ解説します。
他人に話すこと

まずは、継続することを他人に話しましょう。
「毎日筋トレする」「毎日勉強する」など口に出して、家族に説明しましょう。一人暮らしの方などは、SNSで大勢に宣言することも良いですね。
他人に話すことで、後に引けなくなり、自然と「行動する難易度」が下がります。
宣言した行動をやらなければ、その宣言が嘘になり、後ろめたい気持ちに囚われてしまいますよね。「言ったにも関わらずやらなかった」となると、自分にだけでなく、他人に嘘をついてしまったことに後悔してしまいます。自分の信用も落ちてしまいます。
誰もがそのような行いは嫌う傾向があり、その行いを避けるためには「継続せざるを得ない状況にあえて追い込む」という考え方を利用します。継続しなければならないための、いい意味での「言い訳」を自分に作ってあげましょう。
誰かに話せばそれは応援してもらえるかもしれません。そうやって気持ちの面でもポジティブな感情を得られる機会も増えることでしょう。
他人に話す事による裏のメリット
他人に話すと言うことは、その継続する行動の効果を深く知るための機会を創出できます。話すこと、アウトプットするということは、物事を深く理解する効果があります。
他人に話す時には、その行動のメリットやデメリットについて説明することになりますので、「効果的な実践方法」「どういった知識が得られるのか」「その結果、仕事や学生生活に待っている未来」を言語化しましょう。
うまく説明できないようなら、一度、明確に文章化すると良いでしょう。紙やスマートフォンのメモなどでメリットとデメリットを明確に書くのです。
例えば、筋トレを継続したいという場合は、「継続した場合どのような身体的影響が出るのか」を書きます。現在の自分と比較して、どういったプロポーションになるのか、その結果、外出時の見た目に自信が付いたり、服を選ぶ楽しみが増えたり、猫背の解消に繋がる、といったことを文章にしてみましょう。
さらに、デメリットも文章化すると良いでしょう。筋トレの例では、贅肉が落ちない場合にどのような肥満体となるかを想像し、文章にします。
(辛いとは思いますが)運動をしない事で、代謝能力が落ちた結果、どのような体型になるか、どのような病気が発症する可能性があるかを思いつく限り、時にはインターネットで調べた情報なども記載しておくと良いでしょう。
他人に話すための準備として、文章とする事で結果的に継続したい行動に関しての知識が定着し、理解が深まる事で意識が上がるという結果を生みます。
毎日やること

継続したい行動は、可能な限り毎日行いましょう。
まず精神的な理由として、毎日やらないとその継続行為のハードルが上がります。
「毎日連続的に行うこと」と、「一度中断したものを再開すること」はその難易度が違うと言われます。
例えば週に1回、ランニングをするとします。これは逆に言えば「週に6回ランニングしない」ということです。もっと言えば、「週に6回ランニングをサボってもOK」ということを自分に言い聞かせている、と言えます。
この時、人は弱い生き物ですから、楽な方に思考が傾きます。週1回来るランニングをしなければならない日よりも、ランニングをしなくてもよい週6日間の方が好きになります。
週6回やらなくてもよい楽な毎日を過ごした精神状態から、いよいよの週1回がきたときには、そのモチベーションを上げるエネルギーを大量に必要とするようになります。昨日はやならくてもよかったのに、今日は辛いことをしなければならない、という比較を無意識に行うからです。
この場合、誘惑を頑張って振り切り、週6日間かけて落としきったモチベーションを上げなければいけませんが、これが毎日であった場合はその限りではありません。
なぜなら、昨日も、一昨日もその継続的行動を取っていたなら、モチベーションが落ちきらないからです。6日間かけてモチベーションを下げた場合と、昨日からたったの1日をおいて再開する場合では、誘惑を振り切るためのエネルギーが少量で済みます。
精神的にもこれを長く続ければ続けるほど効果を発揮します。なぜなら、例えば1ヶ月続けた行動を、次の日継続できなかった時は、精神的な自責の念が大きいデメリットとなるからです。
「やらなかった」という後悔。「連続記録が途絶えた」という後悔。そんな気持ちを頂くくらいなら、昨日までと同じように行動しようという気持ちが働きやすくなります。
短い時間で終わらせることが重要
毎日継続するには、楽しい、気分がいい、などの感覚を身体に「短時間で」味合わせることが大事です。
例えば筋トレであれば、毎日同じ部位に負荷をかけることは超回復の観点で効率的では無いと言われています。1日などの期間を空けて、筋肉が増強した状態で筋繊維に負荷を掛けることで効果的に筋力アップを望めます。今日は胸筋を重点的に、明日は足腰を重点的に、など日によって分散し、短時間で毎日継続することが重要です。
また、学習などの例では、週一の練習や学習は効果が薄いとも言われます。学校の先生もよく「復習が大事」と子供たちに教えるのは記憶への定着が目的です。
人は忘れる生き物です。知識として定着する事の対義語は、忘却ですが、週に一回の学習ということは、睡眠によって週6回忘れていくということです。
1週間前の夕飯をすぐ思い出せるでしょうか?
ほとんどの人は、思い出すことに時間がかかるか、忘れてしまっていることでしょう。
しかし、例えば、5月17日の夕食の献立を、毎日毎日繰り返し記憶するような行動をとったらどうでしょう。きっと1週間後も覚えていると思います。
1週間前の勉強した内容を、翌週に学習するということは、毎日実践することに比べて定着の速度が遅い、またはほとんどを忘却してしまいます。よほど印象的な学習手段でなかったのなら、ほとんど知識として定着せずに忘れてしまうでしょう。
人生において貴重な時間という資源を投資するのなら、より意味のある効果的な方法で有意義な時間としたいものです。
すべてをやらないこと

継続したい行動は全てをやらないことを意識しましょう。
始めた時はモチベーションが最も高く、考えうる最大努力をしがちです。しかし、考えうる全てのタスクを完遂することは大変な労力であることがあります。
例えば、ジムでみっちり2時間のハードトレーニングをしたとします。すると「かなりキツかった」という印象が残ってしまい、人は楽な方に意識が傾きますから、「明日もまたやろう」という気持ちが薄れてしまいます。
もうひとつ例を挙げるなら、料理の場合です。
全品手作りで作ろうとすると、かなり手間がかかります。1日三食を毎食バランスを考えて用意することは、準備の時間もかかり労力は大変なものです。
全てやろうとすることによって、多くの体力と長時間消費することで、辛かったという印象が根付いてしまい、結果「またやるのか・・・」と億劫に思ってしまいます。明日の自分は今日の自分よりも、モチベーションが低い可能性がありますので、作業を簡単にしてあげる必要があります。
そのためには、継続したい行動の全てをやらず、明日の自分に少ない作業で済むように引き継ぐという考えが重要です。
小さな成功体験を日々感じることができるように、小さな作業を継続しましょう。すると、「小さいことだけれど、毎日続けている」という成功体験から自信を持つことができます。
その結果、「たまにはもうちょっとハードなトレーニングをしてみようかな」とか、「今日は副菜をもう一品調理してみようかな」といった追加の挑戦意欲が起きやすくなります。
「部分的にでもこれだけ継続したのだ」という自信が、継続するためのモチベーションになるのです。
継続した結果得られるもの

私はこれらのコツを活用し、なんとか毎日noteへの投稿を120連続投稿しています。
他人に話すこと、という点では、方々で「noteを書いているよ、是非読んでね!」を宣伝して回っていますし、SNSでも書いた記事のシェアと同時に「毎日投稿しています」と話すようにしています。
毎日やること、という点では、以前週一で土日だけ集中して書こうともしましたが、失敗しました。結局、普段やってないことをたまの休日にやる気が起きず、手がつかないのです。
すべてをやらないこと、という点では、密に練った投稿をするのではなく、一つのテーマを決め、頭に自然に浮かんだ内容や、普段考えたことを飾らない自分の言葉で書くようにしています。
自分の中でまだ結論が出ていないことや、これからどうなるかわからないといった内容、考察が十分でないが共有したい事実、などとコンテンツの精度を下げることで毎日続けることが出来ています。
結果どうなったかというと、もう毎日noteを書かないと落ち着かない、むしろ早く書きたくて仕方がない、といった精神状態になりました。「書くか書かないか」という選択肢はもうありません。書かないといけないと無意識に思うようになり、感情が麻痺しています。
その日の朝になるべく投稿するようにしていますが、急な作業があった場合などに書けない日は、「まだ書いてない」という気持ちに支配され、休憩時間などにささっと書いて投稿するということを愚直にこなすようになりました。
結果的に文章力のトレーニングにもなりますし、Google検索エンジンのキーワード検索1位のワードもあり、自分自身の資本になっていることに大変嬉しく感じています。
私の経験上、感情が麻痺するほどの継続は1ヶ月程度で得られると思います。その結果、普段の生活の一部に継続的な行動を組み込むことができ、ストレスなく続けることができます。
ぜひ、これまで三日坊主になりがちで継続が苦手だった読者の皆さんがおられましたら、この3つのポイントを意識して実践されてみてください。